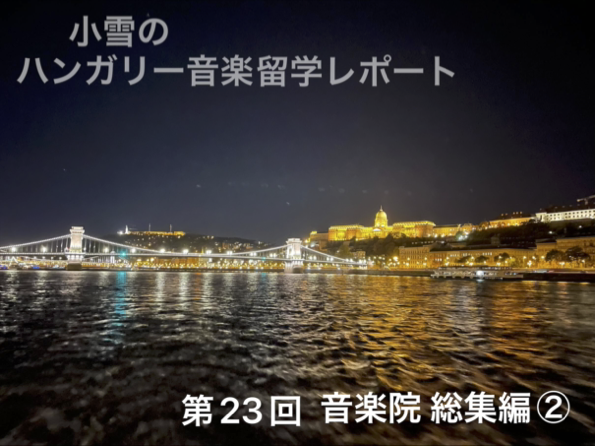2025.10.2
第23回 音楽院 総集編②
今回も総集編と題し、クラスコンサートと試験についてです。クラスごとに毎学期設けられているクラスコンサートは、その学期の集大成として行われる試験ですが、どのような課題があり、どのように試験が行われるのか、また前年度の後期は試験を延期して受けた経験も交えてレポートにします。最後にリサイタル直前の記事として、曲目を選んだ理由なども書きます。
—クラスコンサートと試験
クラスコンサートは、毎週のレッスンで各自の取り組んでいる作品を仕上げていき、自分の師事している先生の主催のもとで開催される、生徒による弾き合いによるコンサートです。それぞれ、実技試験や控えるコンクールなどに向けて成果を発表する場で、いわば本番前の大きなリハーサルとも言えます。全ての先生のクラスコンサートに聴きに行ったわけではないので詳細は曖昧ですが、友人から聞いた話では試験曲を全て通しで弾かされ、計1時間弾く人もいました。そのため他の学年も含めた全員によるクラスコンサートは、約4時間近くかかるそうです。私が師事する先生方は、生徒数が少ないのと、一人の先生は各自時間制限を設けていることから、演奏時間は約20分から30分といったところです。一般にも公開されているので、リスト音楽院の演奏会のホームページから確認できるので、誰でも聴きにいくことが可能です。もちろん実技だけでなく、室内楽にもクラスコンサートがありますが、少し違うのは成績に反映されるところです。この本番に慣れてきて感覚を掴めたところで、学期末にある試験に臨みます。

写真1 実際のクラスコンサートの様子

写真2 試験前の良い機会になります。
実技試験は大学院では試験課題が出されていて、それを前期と後期とで合わせて全てを弾かなければいけません。例を挙げると、練習曲を2つと古典ソナタを1つなど、主要な時代の作品を網羅するように、基礎から近現代の作品まで取り組みます。作曲家も指定されているので、どんな曲が良いか学期始めに先生とよく相談します。それも全学期合わせてそれぞれ3ヶ月程しか準備期間がなく、その間に連休などもある為、他の授業との合間に取り組む必要があります。例年通りにいくと、前期は1月中旬、後期は5月末に行われます。ただ、今回の私の右手負傷のような、急を要する療養などに対する処置もあります。それが、延期試験になります。これは次学期か、年度越しの学期頭に行われ、先生方の予定も照らし合わせて日程が決まります。実技試験は本館の小ホールで行われますが、延期試験はレッスン室で行われました。先生方が両サイドと後ろに控えて弾くことは、なかなか経験したことがないので、緊張と新鮮さを味わいました。成績は生徒ごとに選んだ曲の完成度と演奏姿勢が審査されて、試験を受けた当日か翌日に結果通知をもらいます。


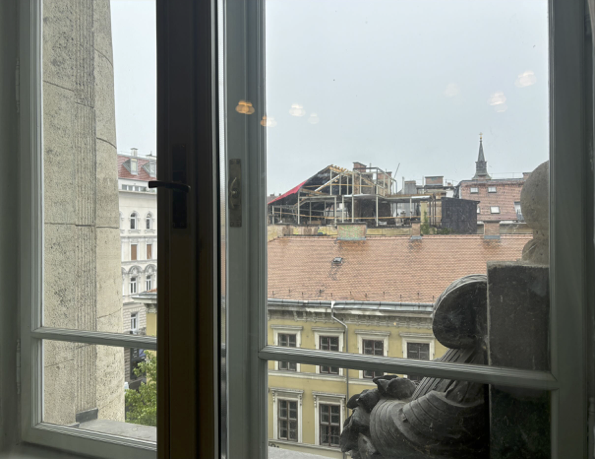
別の階にある大きな部屋。ここでもよくクラスコンサートが開催され、主に室内楽の時に使われます。
—近況報告
9月からの新学期は、大学院の最後の年ということもあり、事務手続きに苦労しました。特に重要なのが、年度末にあるディプロマ終了試験です。これは4月末から6月頭にかけて行われ、指定の課題もなく集大成として自由に選んで良いのです。そこでまず考えなければいけないのが、ソロか重奏かです。ソロは自分自身のリサイタルのように、時間に見合った作品をいくつか選びます。重奏はオーケストラや室内楽団に共演を頼み、協奏曲など大きな作品を選びます。この編成によって弾く場所の確保に入ります。これは事務局から送られて来るオンラインでの申し込みで、担当者との面談日程を取り、そこで小ホールか別館かの場所と、いつが良いかの日程を話し合います。私は何度か対面とメールとのやり取りで、良い時期と場所が確保できたので一安心しました。こうした連絡のやり取りも自分の責任のもと行われるので、無意識のうちに疲れが溜まったりします。
—リサイタルの曲目について
今回のリサイタルにあたって大事なポイントにしたのは、新たな作品への導きです。クラシック音楽といえども様々な作品があり、それは近現代音楽もクラシックのジャンルに含まれています。私はこの留学を経験しなければ、多種多様な作品に出会う事もなかったですし、その用途に応じて選ぶべき作品がどういったものなのかも知りませんでした。色々な作品に出会うきっかけは、先生からの推薦や毎日開かれるコンサート、友達との会話から訪れます。日常的にクラシック音楽に対する意識があり、また身近なものという感覚を持つハンガリー人には驚きました。その意識にだんだんと自分も感化されていき、ブダペスト市内各地で開催されるコンサートに一層脚を運ぶようになりました。新たな作品に出会えるチャンスへのワクワク感や、それを演奏するさまざまな演奏家の発見も、やはり実際の演奏会でしか得られない何かがあると思います。今回のご来場いただいたお客様にも、是非色々な作品に興味を持って頂けたら嬉しいです。
次回からはリスト音楽院の歴史や建物内の紹介に移ります。これまでのレポートで少し写真にて取り上げましたが、どんな大きさで装飾が施されているかなど、私の視点で紹介しようと思います。そして最後に、今回のリサイタルを踏まえた報告も書こうと思います。