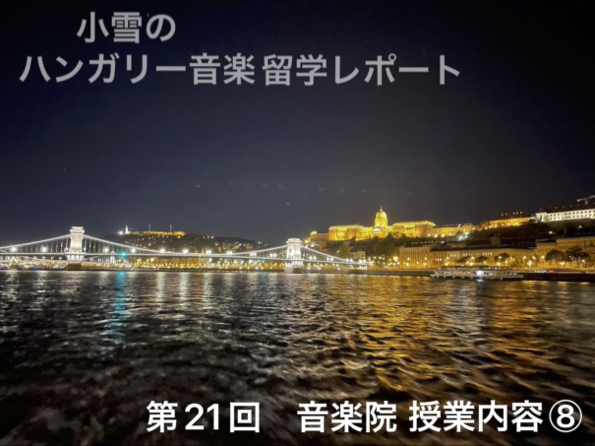2025,9,4
第21回 音楽院 授業内容⑧
今回は、選択科目と区分した授業の「身体の仕組み」についてです。身体が資本である楽器奏者は、どういう使い方が良いのか、また反対に悪いのか。それぞれの楽器ごとに身体の使い方に違いがありますが、特にピアノを弾くにあたって何が重要で理解すべきことなのか、教授職に付かれている先生の指導の元、さまざまな基礎事項を学んだので、その一部を紹介させていただきます。
—身体の仕組み
この授業の大きな目的は、身体をどれだけ自然に使いこなせるかでした。初回の授業から先生が口にしていたことは、どれほど大きな音や速く弾けようと、しっかりと身体の使い方を理解していないと騒音に等しいということでした。レッスンの中で、先生から実際の弾き方をレクチャーしてもらって、側から身体の使い方を確認することはありましたが、これまで身体の使い方そのものだけでのレッスンはありませんでした。9月から12月までの半期のみの授業でしたが、非常に勉強になりました。
初回の授業は、オリエンテーションを交えた自己紹介と授業内容の説明でした。今年からの新たな授業だったこともあり、私を含めた5人の少人数クラスでした。このクラスを知り、興味を持ったきっかけが同期の日本人の子からのクチコミでした。以前、彼女が先生のレッスンを個人的に受けたことがあったそうで、物腰柔らかな指導やコミュニケーションに良い印象を持ったそうです。加えて、あまり見ない授業名「Music is your body」だったこともあって、受講を決めました。自己紹介の後、それぞれが取り組んでいる曲を聞かれ、次回からの課題として1ページ分でも良いので持ってくるよう言われました。授業の流れとして、体操、前回の復習、課題となっていて、この課題の部分で各自取り組んでいる曲を弾きながら、先生から身体の使い方に対して直接指導が入ります。実際に、普段から弾いている曲を演奏することで、良くも悪くも自分のクセが出てくるので、より効き目のある指導が入りやすいそうです。本当にたった1、2ページだけの場合でも、色々なクセがあるんだなと気づきます。
このクラスは少人数で体操を組み込んだ授業なので、全員で円を描くように立ち、等間隔で自由に身体を動かします。軽い準備体操でまず呼吸から入り、浅いものと深いものを交互に、肺だけでなく身体の循環をも意識しながら、リラックスモードに切り替えていきます。次に身体の柔軟体操へ、前後左右に腕や肩、腰を動かして可動域を広げます。この時が一番身体を労っている感覚があり、とても気持ちがいいです。最後に演奏する位置をイメージしながら手を構え、リラックス状態で必要最小限の力の入れ具合を身体で覚えます。この常に良い状態をイメージし、その感覚を身体に覚えさせるイメージトレーニングが大事だと教わりました。
この一連の体操の流れが終わると各自イスを持って、教室にあるアップライトピアノの周りに集まり、代わる代わる順番に弾いていきます。それぞれ弾き終わると、まず先生からざっくりどう感じたか、また身体と連携した手の動きを感じたか、この大きく2点を聞かれます。ここで私たち生徒と先生との、自己分析と見解を照らし合わせていきます。少し肩の上がりが気になる、顔の表情が常に硬い、といった身体からくる音の変化が、特に多く意見としてクラス全員に上がっていました。先生からの指摘を元に、自分なりに気をつけていても、クセとして長年蓄積されていると、最初は良くても次第に元の位置まで戻ってしまう、なんてことが多々ありました。ただ半期と約3ヶ月受講していると、それぞれに変化が起きて、先生からの指摘なしに演奏前や演奏中に、自分で注意すべきところに気づく、新たなクセが出来ていました。この進歩に先生から褒めの指摘をいただくなんてこともあり、成長を感じられた瞬間でした。
—近況報告
この夏は、夏期セミナーに参加をしてきました。開催場所は、クロアチアのプーラという海に面した古代ローマ時代の建物も多く残る、歴史ある街です。このセミナーに参加したきっかけは、現在リスト音楽院で師事している先生が、主催者としていらっしゃったからでした。数ヶ月前にセミナーの案内を聞き、誘われたので参加を決めました。これまでにさまざまなセミナーに数回参加してきましたが、今回初めて日本人一人での参加でした。心許ない感じもしますが、同じリスト音楽院に在籍している友達が数人いたので安心でした。今や、世界各国で開催されているセミナーは、特に多くのアジア人が今期をチャンスと捉え、クラシックの本場でヨーロッパの先生方から指導を受けられると参加されています。そんな背景からも、参加者のほとんどは地元のクロアチア人とヨーロッパ諸国からの人、あと中国人で、日本人がいないのは初めてでした。留学先のリスト音楽院ではたくさんの日本人がいるので、少しは日本語を喋る機会があります。その為、一週間英語で暮らす日々を送ったので、どこか不思議な感覚でした。
【宿泊していた寮】



【ルームシェア式で別館にて食事を摂る。6日間滞在した中で出た食事の一部。】



初日から最終日にかけて、計4回のレッスンを3人の先生方から受けました。一人は現在師事している先生、一人はドイツの大学の先生、もう一人はフランスの大学の先生でした。それぞれヨーロッパでも違うバックグラウンドを持っていると、同じ曲でレッスンを受けてもどんどん違う指摘をもらい刺激をもらいました。毎日、ピアノクラス、弦楽器クラス、室内楽クラスで、クラスコンサートが交互に開催され、私も演奏しました。生徒さんの演奏も個性豊かで、やはり、どっしりとした姿勢で自信溢れる演奏をするヨーロッパの人から多くの発見を得ました。
【用意された練習室】

【近くの教会とセミナー会場での2箇所開催によるクラスコンサート】


【実際に私が演奏した時の様子】

久々に再開した友達とのビーチへのお出かけ、宿泊している寮での新たな出会い、クラスコンサート後の先生とクラス交流会、友達全員でのランチなど、音楽から繋がりを得た経験は新鮮で楽しかったです。
【友達と昼間の空いた時間に行ったビーチ、バスで少し移動すると至る場所にこのようなビーチが点在し、多くの人で賑わっていた。】


—リサイタル開催にあたって
④日本とハンガリーのレッスンの違い
私はレッスンの意義について、あまり深く考えたことがありませんでした。どうあるべきでどうすべきかは全て、先生の指示に従うことばかりに重きを置いていましたが、それはほんの一部に過ぎなかったようです。確かに、何十年と音楽と向き合い、さまざまな知識を培った人からの教えには説得力があります。作品をより良い状態へと仕上げていくのに、先生からの助言は欠かせません。ただ一方で、自分の信念と理想ばかりが目に見え、生徒がその場に置いてきぼりにされることもあります。楽譜からの情報を第一に、研究や調査を元に得た知識を第二に、さらにそこから先生の個人的見解があってこそ、真の音楽解釈だと、リスト音楽院の教授が仰っていました。やはり、どんなに権威のある方でも、教え方に疑問を感じてしまう先生はいます。どの国でも先生と生徒の立場上の違いはありますが、尊敬と礼儀は持ちつつも対等に話し合えるかが、重要なポイントだと思います。こうした内容を、MCの方との対話でお伝えしていきたいと思います。
さて次回からは、総集編と題し、第一弾に課題とレポートに関する内容です。それぞれの授業ごとに提出しなければいけないもの、時には授業内での発表形式での課題もあります。どれだけ良くまとまり、分かりやすい内容であるか、さらに、発表での口頭による説明を含めた仕上がりがどうなのか、といった内容を次回のレポートにしようと思います。