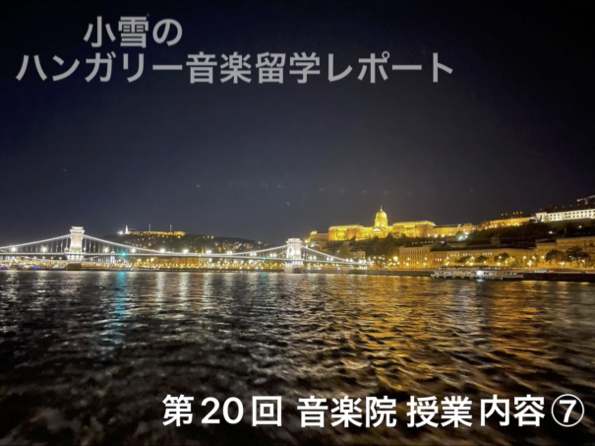2025,8,14
第20回 音楽院 授業内容⑦
今回は、選択科目と区分した授業の「語学」の紹介です。海外での語学の授業は、言語種類も豊富でより細かなレベルでの受講が可能です。毎日のように浴びる他言語を、一から英語で学ぶというなかなか高度なものですが、どんな雰囲気でどんな内容なのかをレポートにしていこうと思います。さらに、引き続きリサイタルに関する内容も新たに追加しますので、是非、最後まで目を通して頂けたらと思います。
—語学
この授業にはいくつかの言語選択があり、英語、イタリア語、ドイツ語、ハンガリー語となっています。それぞれレベルに分けられていて、初級から上級までの中から、さらに最大6段階に細かく分かれています。このレベル別にあたっては、履修登録の時に自分の受けたい授業コマを探し、日程と先生の連絡先を確保します。というのも、初回の授業にてオリエンテーションがあるのですが、言語によって、(特に履修者の多い英語は)受け持つ先生が違う為、初回授業の日程も別々、さらにそのお知らせが一斉メールで送られてきます。このオンラインでの連絡は、個々の責任にも関わって来るので注意が必要です。私が履修したのはハンガリー語ですが、ここでは、初級、中級、上級の3段階にクラス分けされていました。初級は昨年受けた為、中級からのスタートでした。オリエンテーションでは、連絡網や教材までの全ての通知を、Google Classroomで受け取る為、各自クラス別ごとのコードを入力し設定します。その後、次週からそれぞれの授業が開始する、という流れになります。
基本留学生を対象としているので、クラス内での言語は英語での授業になります。内容としては、まず、会話内容や例文などを読みながら発音をチェックし、次に、翻訳を英語で行い先生からのチェックが入ります。この作業は、先生が生徒を指名して行うものではないので、自分で挙手しないとただ座っているだけになります。ここが、やはり日本の授業風景と大きく違い、我先にと意欲的に取り組む姿勢にこちらも自然と感化されていきます。もちろん質問があれば、先生の説明の途中や終わった時にすかさず質問します。あるクラスメイトは、かなり前に確認した内容についてもう一度確認したいと、そこであえて10分から15分ほど時間を設けて、再確認が始まることもあります。それだけ、先生自身も生徒が積極的に学ぼうとする姿に感激しているようで、実際に喜んでいました。

【実際のクラス内の様子、ここではハンガリーの国土面積の歴史について語っている。】
ただ、一つ大きな欠点を挙げるならば、文化トークが多いことです。これは、先生が呼び名を付けたのですが、留学生同士による文化の違いと、ハンガリー文化について意見を交換し合うことです。政治関連から祝日の由来など、多様な話が持ち上がります。特に最近の大きな話題と言えば、キリスト教のローマ教皇が正式に決まりました。長らく、キリスト教の聖地とされるイタリアから、イタリア人が推薦されていましたが、初のアメリカ人の教皇が誕生し、これには賛否両論あったそうです。政治利用されるまでになったのか、あるいは真に選ばれた忖度なしなのか、クラス内ではあまり良い反応は見られませんでした。こういう異文化交流ならぬ意見交換が日常的に行われるのは、外国のラフさの表れです。
—近況報告
少し遡り、6月頭に筆記試験がありました。これまで学んだモーツァルトのオペラの内容の中から、先生が約5つから6つの題材を設定し、そのうちの一つを選択して、レポートを400文字書く試験でした。例えとして、「オペラの登場人物に関して」や「印象的な作曲技法について、作品一つを例に挙げ説明せよ」など、より細かなテーマ設定で複雑なものだったのでかなり苦戦しました。また当然、英語でのレポートになるので、どう順序良く説明し、自分の意見も混ぜながらまとめるかが大変でした。あまり手応え良くなく終わってしまい、案の定、翌日に行われた口頭諮問ならぬ二者面談にて、題材内容から外れた説明が多く、もう少し吟味するようにと指示されました。この授業では、あまり深く学んでこなかった分野だったので色々と大変でしたが、良い機会になったと思います。

【音楽史の授業の様子、パワーポイントを使って先生の説明も交えながらの授業。】
—リサイタル開催にあたって
③ハンガリーについてのトーク内容
今回のリサイタルでは、MCの方を招いてのトークを行うなど、充実したものとなっています。このレポートにてお伝えしていること以外の、友達関係や外部の学生との交流など、音楽院の様子のみならず広い範囲でのトークを予定しています。私自身、多くの疑問を抱えながら留学生活をスタートさせた身なので、今後留学を検討している方への一つの参考となればと願っています。もちろん、今現在のヨーロッパの状況そのものがどうなのか、国境を超えた人同士の日々の交流がどんなものなのかといったことに興味を持ってくださる方にも、是非楽しんで頂ければ嬉しいです。いつも痛感させられ、また責任を感じる「日本人」としての看板を背負う感覚は、何気ない友達との会話でも表れます。「こういう文化はあるの?」や「日本人ってこういう場面にはどうするの?」と、日本に対し興味あるなしに限らず、どれだけ自分の生まれ育った国に対して、知識があり誇りを持っているかは非常に大事なことだと思います。そんな日頃からの経験談も交えてのコンサートに出来ればと思っています。
さて次回は、もう残りわずかとなってきた授業内容ですが、今回と同じ選択授業の「身体の仕組み」についての紹介です。どんな職業であっても、身体が資本であることに変わらないですいが、楽器ごとの身体の使い方に違いがあり、特にピアノを弾くにあたって、身体とどう向き合い日々の鍛錬にあたるのか、教授職である先生の指導の下で行われる授業についてレポートしていこうと思います。