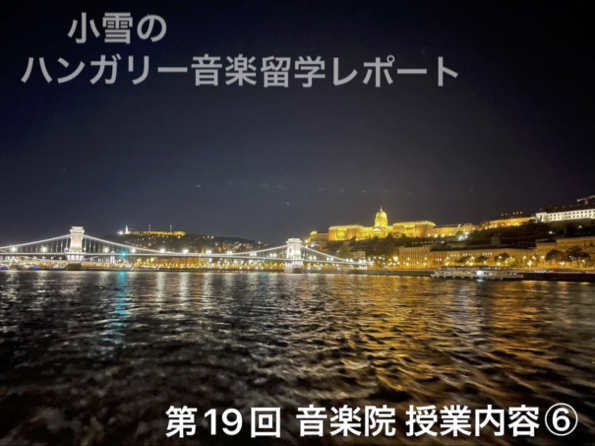2025.7.31
第19回 音楽院 授業内容⑥
今回は、必修科目の座学系と区分した授業の「分析」の紹介をして行こうと思います。更に今回はリサイタルに関する内容と題し、新たな内容を記載します。是非、最後まで目を通して頂けたらと思います。
—分析
リスト音楽院での分析の授業は、私にとって非常に面白いものでした。ほとんど日本と変わりはないカリキュラムなのに、何に対し違いを感じたかというと緻密さでした。今では「音楽」は誰でも知っている言葉ですが、そもそもの「音楽」が何を表し定義しているかについても学び、改めて、人が聞き感じるものには由来と生い立ちがあるのを実感しました。周波数や速度に応じて、耳に感じる心地よさを脳が理解し、人に認知されやすい言葉に置き換え広まったからこそ、来る時代ごとに、教会や宮廷、コンサートホールへと、会場の規模や人数に合わせた音楽の発展が生まれていったのかもしれません。この授業ではハンガリーの代表作曲家であるバルトークについて、彼の生い立ちに1回分の授業が割り当てられました。なんと言っても、彼の故郷こそハンガリーであり、音楽に精通しているハンガリー人であれば、誰しも尊敬の念を示します。どの部屋にも彼の肖像画が飾っているわけではないですが、以前ドイツのシュトゥットガルト音楽大学を訪れた時に、先生の部屋にはピアノの前に座った目線の先に飾られていました。バルトークは演奏のみならず作曲にも力を注ぎ、民俗音楽を確立させた先駆者であります。彼と同様に、同郷のコダーイも民俗音楽の研究に尽力しました。そもそも「民俗音楽」というのは、この世に目に見える形で存在せず、人から人へと口頭で伝承して行く無形文化財になります。彼らは、あえてそれを視覚化し継承させようと、紙と鉛筆を片手に、時には何週間、時には何ヶ月も、そこに住む村人たちと共同生活する中で貴重な財産を、今私たちが見て知ることのできる作品として、この世に残してくれました。その音楽採取過程の中で、新たな音程や独特なリズムが発見されたことで、さらなる音楽の発展に寄与しました。こういう少し難しくも、それぞれの作品と作曲家ごとにどんな背景があったのかを先生の解釈も踏まえて教示していただく授業は、とても勉強になります。
—近況報告
5月に入り、月末にかけては授業が終わりに差し掛かり時間が出来たので、ブダペストの動物園へ行ってきました。私よりも、交換留学のプログラムからで長く住んでいる友人も初めてとのことで、とても興味深くありました。場所は、英雄広場の大きな敷地内から少し外れに近い所で、向かう道中には、テニスコートやトランポリンなどの運動施設的な所もあり、面白い発見でした。動物園はとにかく敷地が広く、全てのエリアを見回るのに約3時間かかりました。ネットの口コミを参照したら、「大人も子供も飽きずに、一日中居られる」との意味は、あながち間違っていませんでした。入場してすぐ左側には、なんと日本庭園のコーナーがありました。置き石や枯山水なるものや、ショーウィンドウの中には盆栽など、多くの日本を代表するものがありました。庭園内にあった池の上にかかった赤橋を、ハンガリー人の学生集団と行き違うさまは、異文化世界を感じさせます。

【動物園の入り口】


【日本庭園の様子。盆栽が至るところにあり、異空間を感じさせる。】
まず始めに、小動物から見ていきました。フクロウやナマケモノ、トカゲやヘビなど、多くの動物がエリア別と個室とで分けられていますが、非常に不思議な空間が漂っていました。その小動物エリアを一通り見て回った最後の建物には地下があり、水族館エリアと繋がっていて、たくさんの見たこともない魚の種類で溢れかえっていました。なんと言っても最大の見どころと言えば、アナコンダがいたことです。もう小さなタイプのヘビでさえ気色悪さに耐えかねないのを、食いちぎった餌が浮遊する大きな水槽の中で、でっぷりとしたその様は目を疑うほどでした。行き交う多くの人の中には外国人の方もいて、世界的に有名な観光場所なことも伺えました。


【至る所に緑豊かな場所がある。】

【ナマケモノ】

【小さなトカゲ】
次に、陸の動物コーナーです。カンガルーやダチョウが一緒くたにされていて、お客の散策用スペースに設けられた柵を超えて自由気ままに散歩する姿は、ヨーロッパらしい風情を感じました。ライオンや熊、ゴリラにオラウータンなど、多種多様に富んだ動物園はなかなか新鮮でした。中盤に差し掛かり、最後のエリアとして見たのが大きな動物です。同じ陸であっても、個体の大きさにより収容範囲が違う為、一つのエリアごとにそれぞれの動物がいました。象やキリン、ラクダやヌーなどは、その存在に圧倒されました。一方側を見れば、先ほど話した運動施設エリアと道路があり、人の生活との隣り合わせで動物園があるのは、日本では考えられない感覚だと思いました。


【自由気ままに過ごすカンガルーたち】


【サイを遠距離と至近距離とで見た様子】
—リサイタル開催にあたって
②選曲理由
今回のリサイタルにあたって主な軸としたのが、留学をしてから学んだことになります。これは日常体験だけに依らず、音楽院での院生としての進展を反映させたかった想いがあり、これが選曲理由となりました。異国の地での生活、ましてや一人暮らしも兼ね備えての生活は、色々な意味での刺激がありました。言語も違う中でのコミュニケーションや、ヨーロッパの基盤である人との即座な意思疎通には、そのスピードに慣れるのに苦労しました。これは、レッスンでの指導内容や取り組む作品決めの際に、日程調整なども含めて全ての事が関係しています。もう何度もこのレポートにて繰り返していることかもしれませんが、生徒個人の考えや意見にリスペクトを示し、耳を傾けようとして下さる姿勢に感激する一方、どれだけ言葉にして相手に伝えられるかも、こちらは常に慮られます。どういう意図があるかは、それぞれの先生により違いはあると思いますが、言葉や目線、さらにジェスチャーなどで、意欲的であるかが判断されます。どう理解したのか?どこに疑問があり意見を求めているのか?そもそもこの質問に対しYESなのかNOなのか?この会話がより良いレッスンと、自身の練習における作品への取り組み方へと繋がっていくのではないでしょうか。こうした背景から、今回の選曲に挙げた作品がこれまでのレッスンで指導され、より良い形へと試行錯誤してきたものになります。
さて次回も、引き続き音楽院の授業内容についてです。ここでは、新たに選択授業へと変わり「語学」の紹介になります。授業内容や、初回授業でのミーティングの様子、先生との会話や生徒同士のコミュニケーションなど、色々と交えてのレポートにしたいと思います。