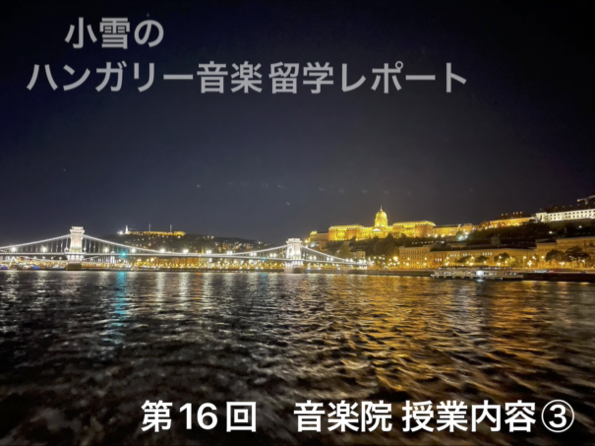2025.4.8
第16回 音楽院 授業内容③
今回は、必修科目である実技系の授業の「現代音楽」の紹介です。さまざまな時代を経て辿り着いた音楽について、どういう要素をもってそう呼ぶのか、どう解釈すれば良いか、さらに他時代の音楽からの継承や、また違いなどにも注目しつつ、実際の授業内容も交えてレポートにしていこうと思います。
—現代音楽
さまざまな要素を取り込んだ複雑さ、それをいくつもの接点が重なり浮かぶ視点、これがやっと気づいた私なりの現代音楽への解釈です。まず始めに背景として、この音楽が発展したきっかけは、世界大戦が大きく影響していると思います。当時、多くの国で政治改革が始まり、国の行く末を大きく左右する国民の支持や思想を、どれだけ勝ち取れるかが最大の課題だったでしょう。この、人々の生活基盤の一部に欠かせないのが芸術です。ここでは、音楽や絵画、写真、小説、詩、陶芸など、多くのものが含まれます。それゆえ、なんとかして政策に対する関心を引きつけ、同時に言論の自由から引き離そうと、芸術への取り締まりが始まり、それが次第に膨んでいきました。この取り組みに巻き込まれた多くの作曲家たちはそれぞれの度合いは違えども、尾行による監視はもちろん、音楽傾向が政治批判につながるかもしれないとの恐れから、演奏会を中止させられたり、作品出版を止められたり、中には、あえて政策支持に寄与するよう作曲依頼がきたり、非常に厳しい状況に置かれることになったのです。この時代背景から彼ら作曲家は知恵を絞り、なんとかして人々の心情を反映させつつも、政策監視下からギリギリ逃れる、そうした新境地を開拓した先にたくさんの音楽の可能性が開かれ、のちに現代音楽という新たなジャンルとして確立したと考えられます。
どのようなことが、ここで言う可能性として表されるか。一つは、色々な作曲技法が挙げられます。どのような音楽が求められるのか、この先に新たなジャンルは存在するのかという、この漠然とした疑問を紐解くかのように、さまざまな作曲のスタイルが誕生しました。ある作品では、同じリズムや音などを何度も繰り返し、その反復を利用し生み出される反響をひとくくりにするもの。他では、独自のリズムや拍子をもって、例えば、テンポの変化をあえてリズムや強弱で表現したりと、より緻密に繊細に書き起こすもの。さらには、楽器に金具などの物を楽器内に取り付け、音の種類に多様性をもたらしたもの。他にもたくさんの技法がありますが、それまでの常識を覆すような取り組みが、新ジャンルへの確立に拍車をかけたかもしれません。加えて、もう一つに、録音技術が挙げられます。今や有名作曲家の多くも、当時の駆け出しや最盛期と晩年などの様子は、楽譜の出版やインタビュー紙によってしか記録されておらず、演奏はその場の聴衆にしか得られない、いわば特権でした。しかし、さまざまな発明により可能となった録音技術の進化により、彼らの多くが自身の作品を、演奏を通して世に残そうとし、のちに大変貴重な資料として現在に受け継がれています。この録音が、緻密に難解とも言える音楽の隅々まで、より多くの幅をもって表現できるようになったのではないかと思います。
ここで本題の授業内容ですが、毎週固定の指定された時間があり、3人グループレッスンの1時間授業となっています。それぞれ、生徒各自に先生から出された現代曲を用意していき、約20分のレッスンでアドバイスを受けます。ここで私が学んだ一番重要なことは、現代音楽を機械的な音楽として捉えないということです。何も突然生まれたものでなく、これまでのバッハやベートーヴェンなどの音楽の基礎が築かれた先の音楽なので、奇天烈にでなく至ってシンプルに解釈するように教わりました。確かに、どこか別の時代の作品を思わせるような要素がたくさんの現代曲から聴こえるのは、音楽の継承を感じられ非常に面白いです。この授業を通して今まで知らずにいた作品を聴ける機会を得たのも、他の人のレッスンを見るのも、ヨーロッパならではのフラット感があったからなのだと思います。
—近況報告
皆さんは現代芸術に対して、どういう感情を抱きますか?今やあらゆる分野で、改革や斬新を武器にさまざまな側面を自由に表現する無限の世界が溢れるようになった気がします。ヨーロッパでは、この現代芸術への関心が非常に高く、多くの作品が制作され、展示会で見る機会がたくさんあります。こうしたいわば新たな試みに対して、ヨーロッパの人たちは何事もまずは挑戦からと全くの抵抗感なく、とても意欲的に取り組んでいます。ここまで人が生み出す芸術へ愛を注げられるのは、国柄の影響も少なからずあるかもしれません。ハンガリーでもここ数十年にかけて、盛んに展示会の開催や、さらにアートショップがオープンされています。この取り組みを知ったのも、今学期から新たに履修した「ブダペストの芸術と展示会」です。







【授業の様子。それぞれの展示会では主に現代アートが飾られ、見る人の思考を一捻りさせる。】
この授業では、色々な新芸術を通して現代におけるハンガリーへの理解を深めていくのが目的で、実際に、ブダペスト市内の展示会やアートショップへ行き、見て触れて体験します。


【展示会へクラスで向かう様子。道中、先生がブダペストの歴史も交えて街を紹介してくれる。】
こういう新たな体験を、ましてや授業で出来るのは良いことだなと思います。あまり日本では、都心には多く機会があるかと思いますが、地方でも是非機会があれば、一度展示会など覗いてみるのも面白いかもしれません。
さて次回も、引き続き音楽院の授業内容についてです。ここでもまた、実技系と区分した授業の「即興」について、どんな授業内容なのか、何を学び実技にも応用されていくのかなど、実際の様子なども含めて紹介していこうと思います。